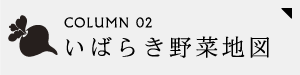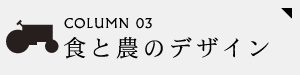大きなものは奥行きが80mもあるというビニールハウスが並ぶ櫻井農園のイチゴ畑。ハウスの中に入るとまるで遠近法のお手本のように、遠くまで高畝(たかうね)が整然と伸びています。合わせて一町二反歩の畑でとちおとめを専門に栽培しています。3世代、半世紀にわたりイチゴを作り続けてきた櫻井農園にとって、トライアンドエラーを繰り返しながら積み上げてきたオリジナルの栽培スキルと、祖父の代から大切に養生してきた土がなによりの財産。この土でとちおとめの特徴を最大限に引き出し、甘味と酸味のバランスの良いイチゴ作りに励んでいます。重厚な甘味と果物らしい爽やかさを合わせ持つ味わいは、匠ならではのおいしさです。
50年の歴史は50通りのイチゴ作り
−櫻井農園におけるイチゴ栽培のこれまでと、現状についてお聞かせください。
櫻井さん:
当園でイチゴを作り始めたのは祖父の代からで、50年ほど前になります。昔は品種もいろいろでしたが、そのうち女峰という品種が台頭してきて、うちでも主力になりました。当時はスイカ、メロン、葉物なども作っていましたが、25〜26年前にメロンの病気が流行ってから徐々にイチゴの作付面積を増やし、20年前から完全にイチゴ専門の農家になりました。
「女峰」を作っていた頃は3月には収穫を終えて、次に同じ畑でメロンを作っていました。それだとイチゴがちょうど盛んに採れている時期に終わりにするしかありません。そこでメロンを縮小していく方向に合わせて、より長期間採取できるよう品種をとちおとめに切り替えて、5月いっぱいまで収穫するようになりました。
−今シーズン(取材は2022年12月)のイチゴはどのような感じですか。
櫻井さん:
今年は例年以上に早くからイチゴの需要がありました。11月にだいぶ温かい日が続いたせいで赤くなるスピードが早くて、前倒しでイチゴが出ています。ところが12月に入って急激に寒くなり、今は生育に急ブレーキがかかった状態です。他の生産地も同様らしく、この時期全国的にいちごの流通が少なく、毎日のように出してほしいとの要望がきています。うちとしては十分に赤くなるのを待ってから出荷したいのですが、クリスマス需要ということもあり、大きさも関係なくとにかく出荷してほしいと言われています。ただ心配なのは、それをやってしまうとこの後が続かなくなってしまうことです。毎年クリスマス時期の調整には苦労していますが、今年は天候の影響でなおさらです。
一般のお客様がお求めになるのは、うちでは年明けてからをおすすめしています。イチゴの味は天候に大きく左右されます。寒さに当たってゆっくりと育ち、晴天の日が続くと甘味が増します。今年は1月半ばから後半にかけて、ちょうど次のサイクルの大粒が採れ始めると思います。
失敗からの学び、旺盛な探究心が今に続いて
−櫻井さんは経験豊富で卓越した技術をもつ生産者として一目置かれる存在ですが、どのようにして栽培の技術を高めてこられたのでしょうか。
櫻井さん:
自分が仕事を始めた頃の鉾田市はメロン作りが今よりもずっと盛んで、多くの農家がメロンを手がけていました。鉾田は気候が良くて何を作っても良いものが採れるので、イチゴに関しても将来性があると感じました。自分自身あれもこれもやるのが苦手で、一つのことに集中したいタイプだということもあり、やるからには良いもの、おいしいものを作りたいと、徐々にイチゴ専門へと切り替えていったのです。
ところがイチゴだけにした最初の年に、管理がうまくできなくて大失敗をしたんですね。それまでもイチゴは手がけていましたから、どうにかなるだろうと思いましたが、結果どうにもなりませんでした。どうしよう、やはり別な作物もやろうかと一瞬迷いましたが、それをやると絶対イチゴがうまくいかないと思い、地元の先輩のところへ教えを乞いにいきました。
その方は栃木県で栽培法を学び、鉾田でイチゴを作っている方です。誰に教えていただくか思案した際に、鉾田市で栽培するのであれば鉾田市のやり方があると思い、地元で上手だと言われているその先輩の元にいったのです。今はほとんどの方がポットで苗を管理していますが、その頃は無仮植といって、イチゴの親から出たランナーを直接地面に植えて苗作りをしていました。当園もそれまでは無仮植でしたが、そこでポット栽培などさまざまな新しい手法を教えてもらい、その時の学びが今の基礎になっています。
−土もイチゴに合わせて設計されているのですね。
櫻井さん:
そうです。栽培法は基本的に大きく変えていませんが、なによりも一番気を使うのが土づくりです。今こうしてやっていられるのも、祖父や父が長年畑の土づくりをしてくれたおかげです。ここ数年の夏の暑さで苗作りが厳しい状況でしたが、病気も出さずに管理できているのは健康な土のおかげだと思います。
イチゴの味を決めるのに重要な堆肥ですが、うちでは自家製の堆肥を使用しています。これが当園の特徴の一つではないかと思います。一般的には堆肥の材料として鶏糞や豚糞などがよく使われますが、うちでは工場で作る際にはじかれた養魚場の魚の餌や、牛豚鶏など家畜を育てるための餌を利用しています。
袋詰めの際にこぼれたりして廃棄される餌が結構な量出るので、その二次利用として紹介されたものです。動物がこれから食べるご飯なのですから、栄養があり健康に良いものしか入っていません。品質的には全く問題ないもので、それを2年間かけて発酵させて使っています。乳酸菌等の良質な菌が豊富で、土中の微生物の働きが活発になり、根の張り方が良くなるなど、イチゴの生育に適した効果が出ています。
適正な対処はつぶさな観察から
−栽培中のいちごの様子は、どのようなところで判断しているのですか。
櫻井さん:
ハウスに入ると皆さん実の様子ばかり目が行ってしまうのですが、元気を見るのは木(親株中心部の茎)と葉っぱですね。特に葉っぱの色はとても気になります。緑色があまり濃すぎてもだめで、ちょうど良い色味があるんです。
花房といってかんざしのようにいくつも花がつく枝があり、少しするとまた次の新しい花房が出てきます。1シーズンにこれを6回くらい出させるのですが、いちごの収穫を切らさぬように、花房と花房の間を空けずに続けて出させるというのが一番苦労するところです。苗の元気を絶やぬよう、休眠させないように管理していくのが難しく、とにかくまめに様子を見て、世話をする必要があります。これをうまくやりきれると、シーズン終盤までおいしいイチゴが採れて、その年の収穫量も大きく変わってきます。
−毎シーズン理想的なイチゴを作るのは大変だと思います。心がけていることはありますか。また、櫻井さんにとってこの仕事の1番の魅力とはなんでしょうか。
櫻井さん:
当園では11月初旬から5月末までの7ヶ月間収穫し続けるので、常にその時々に合わせた対処が必要です。若い時に経験不足で管理が行き届かなかった時は、実がうまくつかなかった。大きくならなかった。父がやっていた時の、例年の半分くらいでした。今思えばそれが良い経験になっていると思います。あの時のあの失敗がなければ、今はなかったかもしれません。
たとえ同じハウス内であっても、すべての株が同じように育つわけではありません。元々の株それぞれの差に加えて、定植した位置によって微妙に日の当たり具合が違ったり、温度の差もあるのでしょう。生長のスピードや実のつき方など、一つひとつが違います。とにかく手間を惜しまずに、様子をみてやるのが一番大事かなと思います。
天候やさまざまな要因により、イチゴの出来には波があります。ただ基本的には、おいしく作るとか、量をたくさん作るということを左右するのは、技術の差だと思います。先に述べた花房にしても、6番目まで出させることができて、シーズン終盤まで品質の良いイチゴを採り続けることができる生産者は多くはありません。そこを目指すには技術が必要です。同じ面積をやってもあまり採れない人もいれば、たくさん採れる人もいる。自分にとってのイチゴ作りは、やったらやっただけ結果がついてくるもの。そこが魅力です。
【取材録】
「イチゴを育てるのに1年では足りない。15ヶ月かかるからいちごなのだと言う人もいます。おいしいイチゴを作るにはそれほど手間がかかり、こまめに面倒をみてやるのが一番の秘訣」と櫻井さん。そんな櫻井さんの作るとちおとめは、光を跳ね返してツヤツヤと真っ赤。かじりつくと口いっぱいに果汁が溢れだし、こぼれてしまいそうにジューシーです。深い甘さとすっきりした酸味。さすが匠と言われるだけある、爽やかで鮮やかな味わいです。3世代、半世紀に及ぶ月日のなかで積み上げてきた研鑽の賜物が、今この手のひらのうえで実を結んでいるのだと感じました。